
Last Up Date 11/29/1997
TOUGE NO Sherpa

峠越えのために連結された機関車は、その勇敢に列車を押し上げる姿から「峠のシェルパ」とも呼ばれる。ここでは歴代のシェルパの中でも、碓氷線104年の歴史のフィナーレを飾ったEF63形電気機関車(通称ロクサン)に焦点をあてて、他の機関車には見られない、「碓氷スペシャル」とでもいうような特殊な装備や峠を登り降りするロクサンの重労働ぶりを簡単に紹介する。

一般に25‰を超えると急勾配と言われるが、碓氷峠はその倍以上(最急勾配66.7‰)もある屈指の超急勾配である。その峠を登り降りするためにロクサンには様々な装置が装備されている。電車との協調運転を行うために、軽井沢側の連結器は回転させることにより2種類の連結器が利用できる、両用連結器が装備されているのはいい例だろう。
峠を登るにあたっては、まず空転防止のため、国鉄・JRのF形(動輪6軸)機関車の中では最大の108tとして大きな粘着力を得ている。また、重心が急勾配のために横川側に片寄るため車体の軽井沢側に軸重調整荷重を取り付けている。さらに逆ハ・リンク式という特殊な台車を用いて、軸重移動という現象を防いでいる。
一般の登山でも言われるように、登ることより降りることの方が遙かに難しいことは、ロクサンにも言えることである。峠を降るにあたっては、登るとき以上に細心の注意が払われる。列車には当然重力が働き、何も手を施さなければ、たちまち暴走してしまう。そういった状況を防ぐために、まず抑速ブレーキとして発電ブレーキを利用している。ロクサン独特のブロワー音も、発電ブレーキにより発熱した抵抗器の熱を外に逃がすためなのである。回生ブレーキでなく発電ブレーキを使うのは、電圧が変化した場合でも常に一定の制動力が得られるためである。また、中間台車に取り付けられたフランジレスの小さな車輪(遊軸装置)により的確に、動輪が空転しても正確な速度が検出できる過速度検出装置が備え付けられている。その速度検出器により、定められた速度を超えると非常ブレーキがかかるようになっている。究極のブレーキとしては、強力な電磁石を台車に取り付け、励磁して制動靴をレールに吸着させる電磁吸着ブレーキが挙げられる。その他にも、乗務員が失神などの緊急状況に備え、1分以上何らかの操作を行わないと警報ブザーが鳴り、5秒以内に解除しなければ非常ブレーキがかかるエマージェンシーブレーキなど、制動関連は挙げればきりがない。
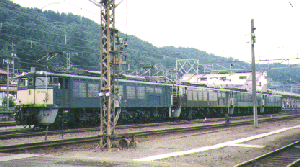
この他にも様々な装置が装備されているが、この場では割愛させていただく。