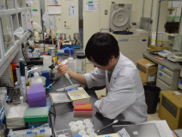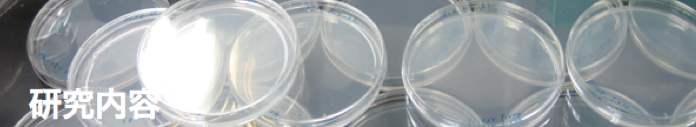遺伝子機能制御学研究室は、応用微生物学を分子生物学の手法を用いて行う研究室です。特に麹菌を中心に糸状菌の研究を行っています。それ以外にも微生物が生産する酵素の研究や応用開発を行っています。
黄麹菌は、酒・みそ・醤油などの発酵食品、いわゆる日本の伝統的なスローフードを作り出す麹として使われる日本を代表する安全な微生物です。また、食品ばかりでなく医薬品製造、異種タンパク質生産などにとっても重要な微生物です。
私たちの研究室は、東北大、東大、名古屋大、製品評価技術基盤機構、産業総合研究所、酒類総合研究所、食品総合研究所などと共同して、1999年に黄麹菌の EST を、2005年末には全ゲノム塩基配列を明らかにしました。ゲノム情報が整備されたことにより、世界中で黄麹菌の研究が活発に行われる様になりました。
私たちは、この黄麹菌が生産する有用タンパク質(特に酵素)の研究や有用タンパク質の生産がどのように行われているか、どのようにすればコントロールできるのかを解明するために、酵素化学的研究や転写制御、翻訳制御、翻訳後修飾などタンパク質とタンパク質生産に関わる研究を行っています。このために タンパク質、酵素、転写制御、翻訳制御、シグナル伝達、形態形成など基礎から応用までの広い範囲について微生物学的、酵素化学的、分子生物学的な研究を進めています。例えば、黄麹菌はタンパク質分解酵素遺伝子を他の近縁種より多く持っていることを明らかにしました。しかし,このたくさんの酵素をどのように使い分けているのかは、全くわかっていません。そこで,これらタンパク質分解酵素をコードする遺伝子の発現や発現したタンパク質の機能分担の解析などの研究を行っています。また、この数多くのタンパク質分解酵素の中から機能性ペプチドなどの効率的製造を可能にする酵素の選択方法の開発、難分解性タンパク質の分解など麹菌や麹菌の生産する酵素を利用するための研究開発も行っています。私たちの成果は、麹菌が生産する酵素などを美味しい食品や機能性の高い食品に利用することができるばかりでなく、カビが原因となる病気や農作物障害に対する医薬品開発、農薬開発などにも役立ちます。
平成18年に日本醸造学会は、麹菌を我が国の「国菌」として認定しました。
国鳥は「キジ」、国花は「桜」、国蝶は「オオムラサキ」等と同様に「麹菌」は日本人にとっても最も大切な生物の一つであるということです。