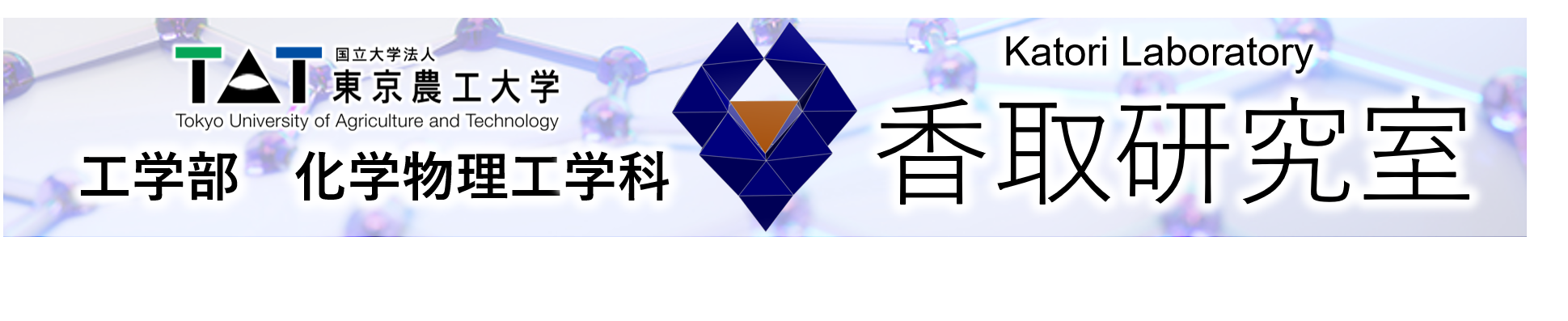2023年度の論文紹介
第1回(4/19):若杉和弘(M2)
57Fe Mössbauer study of stoichiometric iron based superconductor CaKFe4As4: a comparison to KFe2As2 and CaFe2As2Sergey L. Bud’ko et al., Philos. Mag. 97, 2689 (2017).
超伝導転移温度が31~36 Kとかなり高い鉄系超伝導体の新しいファミリーとしてCaKFe4As4(1144) 化合物( A = K,Rb,Cs)が発見された。この系は超伝導以外の相転移がなく、 Mössbauer効果分光法による超伝導転移時の超微細パラメーターの変化を調べることを可能とする。そこで超伝導転移温度が35 Kである単結晶CaKFe4As4を用いて、CaFe2As2やKFe2As2と超微細パラメーターの温度依存性を比較し、超伝導転移との関係を調べた。超微細パラメーターに超伝導転移時の特徴的な変化は確認されなかったが、 CaKFe4As4はCaとKが交互に積層しているという見解と一致する結果を得た。
第2回(4/26):久米田理桜(M1)
Spiral spin-liquid and the emergence of a vortex-like state in MnSc2S4Shang Gao et al., Nature Physics 13, 157 (2017).
近年、スピンが螺旋として集団的にゆらぐ新しいタイプの螺旋状態、螺旋スピン液体の存在が予測されている。本研究では、中性子散乱法を用いて、MnSc2S4における螺旋スピン液体の存在を、逆空間における螺旋伝播ベクトルの連続面である「螺旋表面」を直接観測することにより実験的に証明した。また、螺旋スピン液体の多段階秩序化挙動を解明し、磁場印加時に渦のようなTriple-q相を発見した。この結果は、MnSc2S4の螺旋スピン液体状態のモデルとして、ダイヤモンド格子上のJ1-J2ハミルトニアンが有効であることを証明するとともに、フラストレート相互作用による磁気渦格子の新しい実現方法を示している。
第3回(5/17):伊藤正明(M1)
Majorana quantization and half-integer thermal quantum Hall effect in a Kitaev spin liquidY. Kasahara et al., Nature (London) 559, 227 (2018).
Kitaev模型は結合方向に依存した3種類の異方的な相互作用を有する模型であり、基底状態の厳密解が量子スピン液体であると予言されている。量子スピン液体は、量子コンピュータを動かす基本粒子となるMajorana粒子や非可換anyon粒子が現れるとされ、近年盛んに研究されている分野である。本論文の研究では、量子スピン液体の候補物質であるハニカム格子2次元磁性体α-RuCl3の熱ホール効果を測定し、熱ホール伝導度が磁場に対して一定値(プラトー)をとることが示された。その測定値は電子系の量子ホール効果状態で観測される値の半分に量子化されており、通常のフェルミオンの半分の自由度を持つ中性の粒子、すなわちMajorana粒子の存在が示唆される結果となった。
第4回(5/24):北村昌大(M1)
Skyrmion phase and competing magnetic orders on a breathing kagomé latticeMax Hirschberger et al., Nat. Commun. 10, 5831 (2019).
磁気スキルミオンは、キラルな磁性体等の非中心対称な磁性体で実現されている。これを中心対称な磁性体に拡張することは新たな磁気特性と機能性の向上をもたらす。本論文では中心対称金属化合物Gd3Ru4Al12において、大きなトポロジカルホール効果と2.8 nmという小さな非整合らせんピッチを持つスキルミオン格子(SkL)相を実験的に観測し、Gdのブリージングカゴメ格子を実現したことを報告する。SkLを含むいくつかの磁気構造は、共鳴X線回折と中性子小角散乱によって決定され、ローレンツ透過型電子顕微鏡を用いて、SkL相とらせん相を直接観察した。いくつかの相が競合する中で、SkLは熱揺らぎによって安定化されることを発見した。
第5回(5/31):若杉和弘(M2)
Effect of hydrostatic pressure on the superconducting properties of quasi-1D superconductor K2Cr3As3J. P. Sun et al., J. Phys. Condens. Matter 29, 455603 (2017).
新たに発見されたTc = 6.1Kの準1次元超伝導体K2Cr3As3で、スピン三重項クーパー対をもつ超伝導が報告されている。しかし、本当にスピン三重項超伝導が実現されているかは議論が続いている。そこで、臨界磁場に静水圧印加が及ぼす影響の観測とそれによるスピン三重項超伝導の強磁性揺らぎへの応答の確認を行った。加えて物理圧力と化学圧力の効果の比較を行った。その結果、物理圧力上昇に伴い上部臨界磁場のパウリ常磁性限界と軌道限界のクロスオーバーが起こることが示唆された。
第6回(6/7):久米田理桜(M1)
Spin-orbital entanglement in d8 Mott insulators Possible excitonic magnetism in diamond lattice antiferromagnetsFei-Ye Li and Gang Chen, Physical Review B 100, 045103 (2019).
Ni2+ 3d8 局在モーメントを持つダイヤモンド格子反強磁性体NiRh2O44に関する最近の研究に触発され、3d8 局在モーメントを持つダイヤモンド格子反強磁性体の特異なスピン・軌道物理を一般論として理論的に探究する。局在モーメント間の超交換相互作用は、通常、磁気秩序に有利である。3d8イオンの電子配置は、上部のt2g準位の部分的な充填と下部のeg準位が完全に埋まっているために、原子スピン軌道相互作用は線形オーダーで活性化し、単一イオン極限では局在モーメントが凍結されたスピン軌道もつれ一重項が有利となる。このように、スピン軌道もつれは超交換と競合し、スピン軌道一重項と磁気秩序を分離する量子臨界点まで系を追い込む可能性がある。さらに、磁場と一軸圧力の効果について調べた。磁場に対する非自明な応答は、局在モーメントの根底にあるスピン軌道構造と密接に関連している。ドープや圧力などの将来の実験について議論し、異なる電子配置間の対応関係を指摘する。
第7回(6/26):伊藤正明(M1)
Cu2IrO3: A New Magnetically Frustrated Honeycomb IridateM. Abramchuk, et al., J. Am. Chem. Soc. 139, 15371 (2017).
本研究では、新たなハニカム格子層状化合物であるCu2IrO3について報告する。この物質は、Na2IrO3中のナトリウムを銅で置換することによって合成される。ハニカム格子上にIr4+が配置され、および結合角が120°に近く、前駆体であるNa2IrO3よりも層間距離が大きいという特徴から、Cu2IrO3はKitaevスピン液体状態に幾何学的に近いことが示唆される。さらに、短距離の相関に由来する10 K以下での磁気転移や顕著なフラストレーションいった観測結果は、この物質におけるKitaevスピン液体の実現可能性をさらに支持している。
第8回(7/19):北村昌大(M1)
Structure and properties of the kagome compound YBaCo3AlO7M. Valldor, et al., Physical Review B 78, 024408 (2009).
YBaCo3AlO7の単結晶をFZ法で合成した。(Co/Al)O4四面体はカゴメ格子を形成し、幾何学的フラストレーションが生じる。X線回折測定から、YBaCo3AlO7は空間群P63mcに属し、a=6.28098(3) Å、c=10.21200(5) Åであることが確認された。残留磁化の緩和、転移温度付近での磁化率の周波数依存性、凍結温度でのエントロピー変化の欠如が観測された。このことからYBaCo3AlO7の低温での振る舞いは、反強磁性相互作用を有するスピンがランダムに凍結したスピングラスあるいは「クラスター・グラス」であることが示唆される。
第9回(10/12):若杉和弘(M2)
Different response of the crystal structure to isoelectronic doping in BaFe2(As1−xPx)2 and (Ba1−xSrx)Fe2As2M. Rotter, et al., Physical Review B 82, 014513 (2010).
鉄ヒ素系の超伝導はキャリア濃度を変化させずに超伝導が発現するといった、銅酸化物とは異なる特徴を持つ。しかし、結晶構造、磁気秩序、超伝導の間の詳細な関係性は解明されていない。そこで、化学圧力効果では説明がつかないBa1-xSrPxFe2As2と化学圧力効果による超伝導の誘起があるといわれるBaFe2As1-xPxの構造データを、フルポテンシャル密度汎関数理論(DFT)計算によって得られた理論モデルと比較した。超伝導発現の前提となるSDW秩序の抑制が単純な体積効果のものかを確かめることを目的とした。そして、結晶構造の微妙な変位に依存していることを示す。
第10回(10/19):久米田理桜(M1)
Antiferromagnetic and Orbital Ordering on a Diamond Lattice Near Quantum CriticalityK. W. Plumb et al., Physical Review X 6, 041055 (2016).
本論文は、スピネルFeSc2S4粉末試料の中性子散乱測定を行い、11.8(2)Kで起こるこれまで観測されていなかった磁気秩序転移を明らかにした。磁気秩序は、Fe配位硫黄四面体を歪ませ、軌道縮退を解除する微小な立方晶-正方晶構造転移に続いて起こる。軌道秩序は実際には長距離ではなく、磁気相関長を制限する有限サイズのドメイン上で起こる。1 GPaの静水圧をかけるとこのネール状態は不安定化し、転移温度は8.6(8)Kに下がり、磁気スペクトルの重みはより高い励起エネルギーに再配分されるようである。秩序モーメントm2=3.1(2) μB2と揺らぎモーメントδm2=13(1) μB2の相対的な大きさから、FeSc2S4の磁気秩序状態は劇的に再正規化され、臨界に近いことがわかった。
第11回(11/09):伊藤正明(M1)
NiAs-derived cyanamide (carbodiimide) structures – a group-theoretical viewR. Pöttgen et al. Zeitschrift für Kristallographie 238, 95(2023).
NCN2-で表される「カルボジイミドイオン」は、金属カチオンと結合することによって多様な種類の金属カルボジイミド化合物となる。酸素イオンを始めとした単原子アニオンとは異なり、カルボジイミドイオンは結合するカチオンのサイズや電荷、共有結合の寄与に依存して、その一次元の構造を歪ませる。本論文では、NiAs型構造を基本としたカルボジイミド化合物に着目し、そこから派生していく様々なカルボジイミド化合物群をBärnighausen treesと呼ばれる視覚的な表現を用いて説明することで、カルボジイミドイオンの幾何学的な構造によって拡張された空間群のバリエーションとその対称性低下の過程を明らかにする。
第12回(11/16):北村昌大(M1)
Breathing pyrochlore magnet CuGaCr4S8: Magnetic, thermodynamic, and dielectric propertiesM. Gen et al. Physical Review Materials 7, 104404 (2023).
CuGaCr4S8の結晶学的・磁気的性質を調べた。放射光X線回折実験と構造精密化により、CuとGa原子が交互に四面体のAサイトを占め、ブリージングパイロクロア格子を形成していることが示唆された。Cr4S8はゼロ磁場中31 Kで構造歪みを伴う磁気転移を起こすことから、スピン-格子相互作用が幾何学的フラストレーションを緩和していることが示唆された。パルス強磁場を印加すると、40 Tで鋭いメタ磁性転移が起こり、その後103 Tまで1/2磁化プラトーが続く。これらの相転移は誘電率の異常を伴い、低磁場相にらせんスピン相関が存在することを示唆している。密度汎関数理論の計算から、CuGaCr4S8はCuInCr4S8と同様に、小四面体内と大四面体内でそれぞれ反強磁性と強磁性の交換相互作用が支配的であることが示唆された。
第13回(11/30):千野根広大(B4)
Vanadium-based superconductivity in the breathing kagome compound Ta2V3.1Si0.9H-.X. Liu et al. Phys. Rev. B 108, 104504 (2023)
V系カゴメ金属における超伝導は、フラットバンドとトポロジカル電子構造に関連した競合する競合基底状態を示すことから、最近大きな関心を集めている。今回、超伝導転移温度が7.5KであるTa2V3.1Si0.9を発見した。これはカゴメ金属における常圧での超伝導転移温度としては過去最高である。Vイオンが2次元のブリージングカゴメ構造を形成するが、2つの異なるV-V間距離の長さの差はわずか0.05Åであり、完全なカゴメ構造に非常に近い。また、今回の実験結果から、Ta2V3.1Si0.9がパウリ限界に近い、大きな上部臨界磁場を持つ中程度結合のII型超伝導体であることが示された。DFT計算では、Van Hove特異バンドがフェルミエネルギーに位置しており、これは本物質で観測された比較的高いTcを説明する可能性がある。さらに、電子-フォノン結合計算から、V原子の面内振動が超伝導の駆動に重要な役割を果たしていることを示している。
第14回(12/07):吉良春希(B4)
Recent Progress on Mixed-Anion Materials for Energy ApplicationsK. Maeda et al. Bull. Chem. Soc. Jpn. 95, 26–37 (2022).
O2-、N3-、H-などの複数のアニオンが同一化合物中に含まれる混合アニオン化合物が近年注目されている。混合アニオン化合物は、陽イオンに複数のアニオンが配位した特異な結晶構造を持つため、触媒、電池、超伝導体など様々な化学・物理分野への応用が期待され、根本的に新しい機能を持つ物質の開発が期待されている。本論文では、文部科学省混合アニオン化合物プロジェクトによる新規混合アニオン化合物の開発について、光触媒・光電極、蛍光体、二次電池部材、導電体、熱電材料などを中心に、最近の進捗状況を紹介する。
第15回(12/14):庄司晴紀(B4)
Observation of magnetic field-induced second magnetic ordering and peculiar ferroelectric polarization in L-type ferrimagnetic Fe2(MoO4)3A. Tiwari et al. Physical Review Materials 6, 094412 (2022).
Fe2(MoO4)3の合成に成功し、その特性を磁化率、比熱、誘電率の異常から評価した。これは秩序温度TN1 ∼ 12 KのL型フェリ磁性体のプロトタイプとして機能し、さらに、磁場によって誘発されるTN2での新たな磁気相転移が観測されました。これらの現象は、既知のマルチフェロイックスとは異なり、複雑な温度および磁場依存のスピンと格子構造に関連している可能性があります。
第16回(1/11):金貴美愛(M1)
Assessing Thermodynamic Selectivity of Solid-State Reactions for the Predictive Synthesis of Inorganic MaterialsMatthew J. McDermott et al. ACS Cent. Sci. 9, 1957–1975 (2023).
無機材料の合成において最適な反応経路を選択する為の理論的な手法は限られおり、その選択は研究者の経験と直観に大きく拠っている。本論文では、固体反応における不純物相形成の熱力学的選択性の強さを示す指標C1およびC2を提案し、次のようにその有用性を検証した。既存の文献に存在する3,520件の反応を分析し、うち人気の40物質の合成についてランク付け・評価を行った。また、指標を用いた合成計画ワークフローに則って、Materials projectの第一原理計算データからBaTiO3の82,985件の反応経路を想定し、これらをランク付けして9つの反応を実行・分析した。この9つの反応経路の特性評価により、提案した選択性指標がXRDで観察された目的相・不純物相の生成と相関していることが明らかになった。さらに、従来の合成法より短時間かつ不純物の少ないBaTiO3の反応経路の発見により、前駆体の選択時に主相に含まれない元素を追加した複雑な化学を考慮することの重要性が強調された。本論文の提案するフレームワークは、予測合成の理論的基盤を提供し、既存の反応の最適化や新物質の探索、今後の自動合成の発展に役立つ。