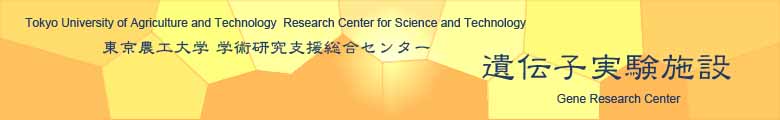第10回遺伝子実験施設定期公開セミナー(平成13年3月22日)
平成13年3月22日(木)午後3:00〜6:00
会場:東京農工大学農学部2号館講義室101
プログラム1
「アジアに生息する Bradyrhizobium 属根粒菌の遺伝的多様性」
東京農工大学農学部助教授 横山 正
私たちは,タイ国で栽培されているダイズ(Glycine max)やリョクトウ(Vigna radiat)に根粒を形成する熱帯Bradyrhizobium 属根粒菌やアジアを起源とする ササゲ属(Vigna)アズキ亜属(Ceratotropis)の各植物種に着生する Bradyrhizobium 属根粒菌の分子系統解析を行っている。今回は,タイ国各地の畑で採取したダイズやリョクトウ の根粒菌,タイ国の非耕作地に自生しているアズキやリョクトウの近縁野生植物から分離した根粒菌,および日本各地のダイズ畑で分離されたダイズ根粒菌間で,共生遺伝子群や系統分類の指標となる遺伝子群にどのくらい違いがあるのか紹介する。
プログラム2
「ミヤコグサ根粒菌のゲノム構造解析」
かずさDNA研究所研究員 金子貴一
根粒菌はマメ科植物の根に根粒形成を誘導し、根粒内部で窒素固定をおこなう土壌細菌である。我々はミヤコグサの根に共生する根粒菌、Mesorhizobium loti MAFF303099のゲノムの全塩基配列解析をおこない、2000年12月に完了した。この解析結果はRhizobase(http://www.kazusa.or.jp/rhizobase/)で公開している。本セミナーでは、ゲノム構造解析法と解析からどのような情報が得られたかの2点について紹介する。
プログラム3
「ミヤコグサ研究の現状と2つのhypernodulation変異体の原因遺伝子について」
東京大学大学院総合文化研究科助手 川口正代司
ミヤコグサ共生変異体の遺伝解析から,根粒数と器官形成に影響する13の遺伝子座を同定した.それらの中から,野生型より根粒を多く着生するastray 変異体とLjsym 78 (har1)変異体の原因遺伝子クローニングの現状を紹介する.Ljsym78 は典型的なhypernodulation変異体であり,Gifu, Miyakojima間のDNA多型に基づくポジショナルクローニングの過程で,ダイズsupernodulation変異体nts-1との遺伝的関連が示唆された.一方,astray 変異体はシロイヌナズナのhy5 変異体と似た表現型から原因遺伝子がクローニングされた.遺伝子産物のC末はHY5と高い相同性を有していたが,N末にはzinc finger motifと酸性領域が付加され,マメに特徴的な構造を有していた.ミヤコグサのモデル化にむけた基盤研究の現状についても紹介する.